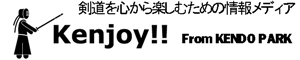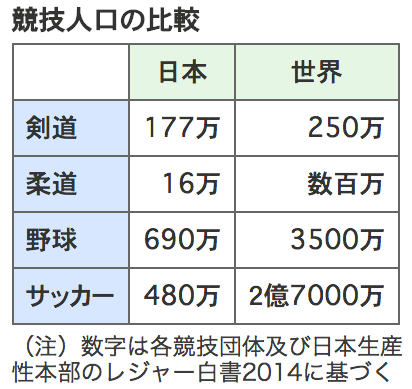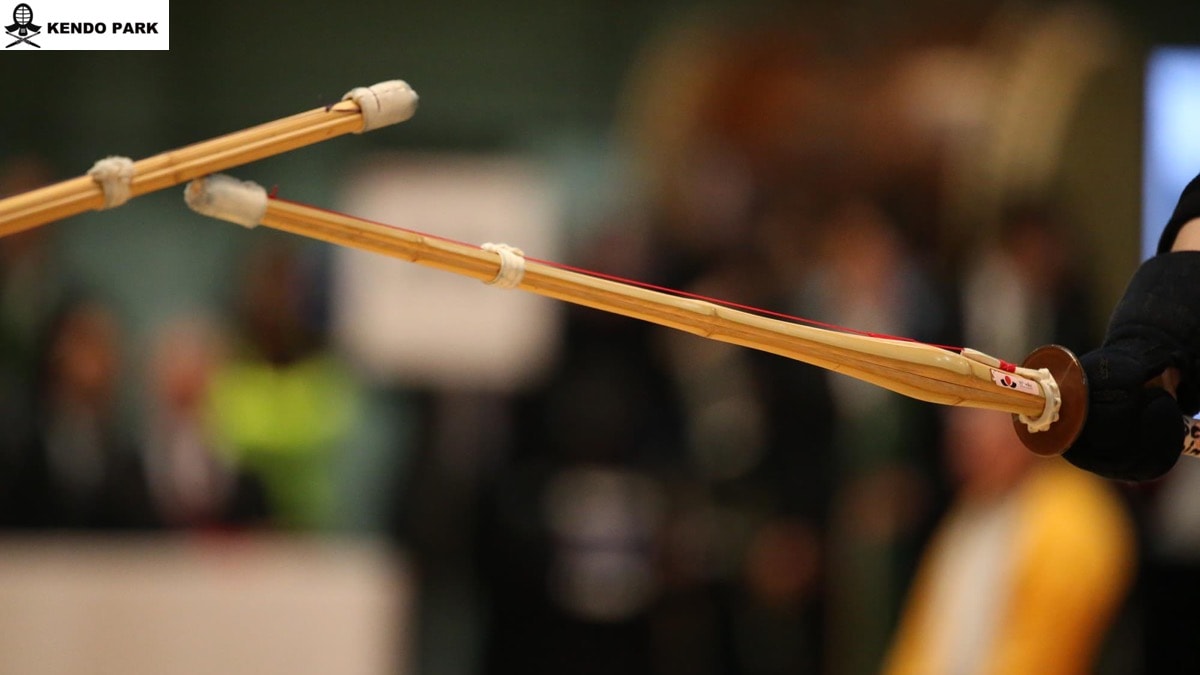▼剣道日本復刊記念コラム▼
「ジャイアントキリングの科学 〜Team USAの奇跡(3)〜」
〜剣道日本編集長 安藤雄一郎〜
月刊剣道日本元編集長の安藤雄一郎氏による連続コラムの第三弾。
アメリカが日本を破った”あの試合”のバックストーリーを、連続コラムにてお届けします。

前回まで:
【ジャイアントキリングの科学〜Team USAの奇跡(1)〜】
【ジャイアントキリングの科学〜Team USAの奇跡(2)〜】
|戦略と実力の融合
アメリカは日本戦に向けてポジションも変更してきた。
サンディ・マルヤマ、ダニエル・ヤング、フミヒデ・イトカズ、クリストファー・ヤング、マーヴィン・カワバタの順である。
前戦のカナダに対しては、カワバタが副将、クリスが大将であった。
二人を入れ替えた意図はこうだ。
アメリカのポイントゲッターはヤング兄弟である。
しかし、ヤング兄弟以外のメンバーが負けてしまった場合、カナダ戦のオーダーだと「●○●●」(=1 – 3)で大将戦を迎えてしまう。
つまり、クリスが戦いを迎える前にチームが負けている、という状況になってしまう。それだけは避けたかったのだ。
先鋒戦。並々ならぬ気合を見せたアメリカのサンディ・マルヤマだったが、対する内村良一(警視庁)がそれ以上の気迫を見せた。
内村の真骨頂とも言える小手が炸裂して日本がリードを奪う。
「やっぱりこのまま日本が押し切るのだろうな」
と私は思ったし、アメリカ陣営にもそんな空気は流れていたようだ。
それを打ち破ったのが次鋒・ダニエルヤングであった。
一本目の小手は下から差し込むような小手。二本目は小手に対しての返し面。
どちらも、有効打を「取る」以上の「もぎ取る」気迫が感じられた。

画像出典:flickr “USA KENDO TEAM” By simulacre

|歴史を変えた後衛二人
この日(団体戦)、初めて日本人選手が負けた。
それまで全試合で「5─0」で勝っていたこともあって、これで風向きが一気に変わったように思った。
そして、私は「これは日本にとってかなりやっかいな事態になったな」と思った。
なぜなら、アメリカの中堅・フミヒデ・イトカズは二刀を使う選手だったからだ。
かつて、あの栄花直輝氏も世界大会で二刀の選手と戦っているが、引き分けている。
韓国人であっても二刀には苦戦することを知っていた。
なので、「この試合(中堅戦)は引き分けになっても不思議ではない」と思っていた。
しかし、日本の寺本将司(大阪府警)は初の二刀との対決にも関わらずみごと二本勝ちをおさめた。
2─1で日本がリード。アメリカは主将・クリストファーヤングが登場する。
負けたら当然チームは敗北。しかし、引き分けてもチームの勝利は限りなく遠ざかる。
この当時、ヤングは東京で仕事をしていたが、滞在中は警視庁の朝稽古に参加していた。
朝、激しい稽古をした後、勤務先に向かっていたのである。
警視庁では、日本代表の選手とも稽古をしていた。
しかしヤングは、「稽古と試合とは別。相手を警視庁の選手と思わず、一人の選手と考える」気持ちで試合に臨んだ。そして、みごと、警視庁の選手から面を二本奪ったのである。
アメリカの大将・カワバタは、代表選手の中で唯一東海岸に暮らす選手である。
準々決勝のカナダ戦では敗れている。実力差を考えれば日本のほうが圧倒しているはずだ。
しかし、大将戦が始まるときには、となりの試合場でおこなわれていたもうひとつの準決勝(韓国対台湾)が早々に終わっており、観衆のすべての目がこの試合に注がれていた。
明らかに異様な空気が流れている、と私は感じた。
そして、追いついた側と追いつかれた側の心理が試合にも出たように思えた。
カワバタは小手を二本決め、歴史的勝利をあげたのである。
【大将戦:マーヴィン・カワバタ vs 清家宏一】
動画出典:kendoUSA(2007/04/26 公開)

|”韓国ではなくアメリカ”という驚き
私が初めて世界大会を見たのが1997年の第10回大会だったが、決勝戦では韓国に0─1でリードを奪われてからの逆転勝ちであった。
それも宮崎正裕、石田利也という超越した力を持った二人だったからこそ逆転できたと感じていた。
※参考:【’97 世界剣道選手権の回顧録】全日本剣道連盟副会長 福本修二
第11回大会でも韓国を相手に大将戦に持ち込まれ、このときは日本の負けを覚悟したが高橋英明が信じがたい集中力を発揮して勝利を収めた。
間近で見ていて、鳥肌が立つ思いだった。
第12回大会は現地で見ていないが、「ただ一撃に賭ける」のテレビドキュメンタリーを通じてその様子を知っている人も多いだろう(代表戦の末に韓国に勝利)。

私は、それほど遠くない未来に、韓国には負けるかもしれないと思っていた。
だからまさかアメリカが日本を破るとは想像もしていなかった。
そして韓国はまだ団体戦で日本に勝ったことはない。
なぜアメリカは日本に勝てたのだろう。
あれから12年、改めて主将のヤングに話を聞いてみた。
取材・文:安藤雄一郎
剣道具専門セレクトショップ【KENDO PARK】